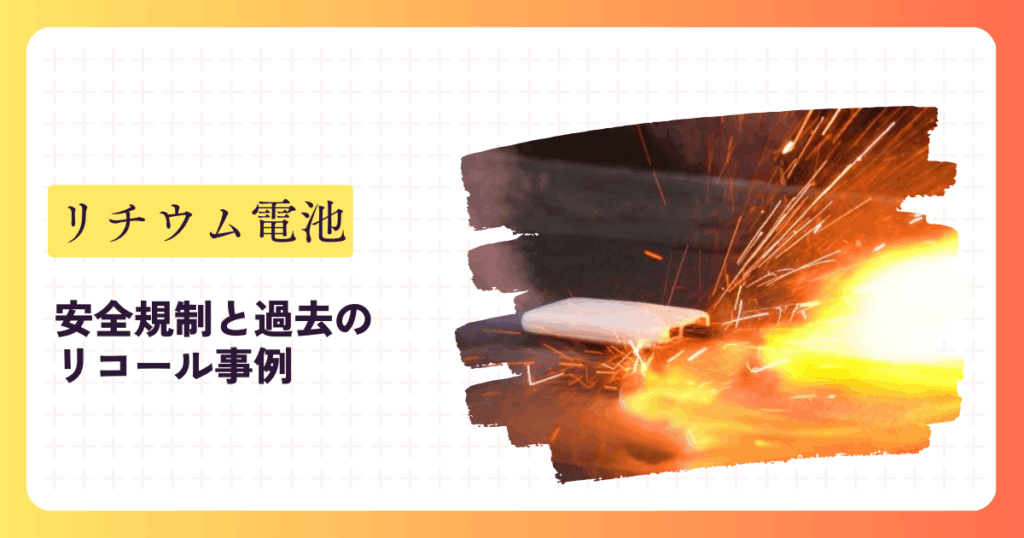制度を知ることで『安心して使える』が実現する
リチウム電池は、私たちの生活に欠かせない技術となりました。
しかし、その高性能さゆえに、発火や爆発といった重大事故のリスクも伴います。
こうしたリスクに対して、国や業界はさまざまな安全規制や制度を整備してきました。
この記事では、リチウム電池に関する安全規制や過去のリコール事例を整理し、消費者が安心して使うために知っておきたい制度情報をわかりやすく解説します。
① 電気用品安全法とPSEマーク:表示の意味と確認ポイント
日本国内で販売されるリチウム電池には、電気用品安全法(PSE法)に基づく表示義務があります。
PSEマークは、製品が技術基準に適合していることを示す証明であり、以下の情報が表示されている必要があります
- PSEマーク(丸型またはひし形)
- 輸入事業者名
- 定格電圧・容量・極性
- 原産国表示
消費者は、購入時にこの表示があるかを確認することで、最低限の安全基準を満たしているかを判断できます。

② 国際輸送規則(UN38.3など):輸送時の安全確保
リチウム電池は、国際的にも「危険物」として扱われるため、輸送には厳格な規則が設けられています。
代表的なものに、以下のような規則があります
- UN38.3試験(国連勧告に基づく輸送試験)
- IATA(国際航空運送協会)による航空輸送規則
- PI965~PI967の梱包基準
特に、満充電状態での輸送は禁止されており、航空会社はUN38.3のサマリー提示を義務付けています。
③ リコール事例の傾向と教訓:事故はなぜ起きたのか
過去には、リチウム電池を内蔵した製品で火災や発煙などの重大事故が発生し、リコールに至った事例があります。
たとえば、2025年8月には、アンカー・ジャパンが輸入した充電器で火災事故が発生し、7件の重大製品事故が報告されました。
事故の原因は、製造不良や過充電保護回路の不備などが多く、制度的なチェックだけでなく、製品選びの慎重さも求められます。
④ 消費者ができる確認ポイント:制度と製品の両面から安全を守る

制度が整っていても、消費者がその情報を知らなければ意味がありません。
以下のようなポイントを意識することで、事故リスクを大きく減らすことができます:
- PSEマークの有無を確認する
- 輸入品は販売事業者の表示をチェックする
- リコール情報を定期的に確認する(消費者庁・NITEなど)
- 輸送時は満充電を避ける
まとめ:制度と技術の両輪で安全を守る
リチウム電池の安全性は、製品の技術だけでなく、制度的な裏付けによって支えられています。
消費者が制度を理解し、製品選びや使用方法に反映させることで、事故を未然に防ぐことができます。
安全な社会の実現には、制度と技術、そして使う人の意識が三位一体であることが求められます。
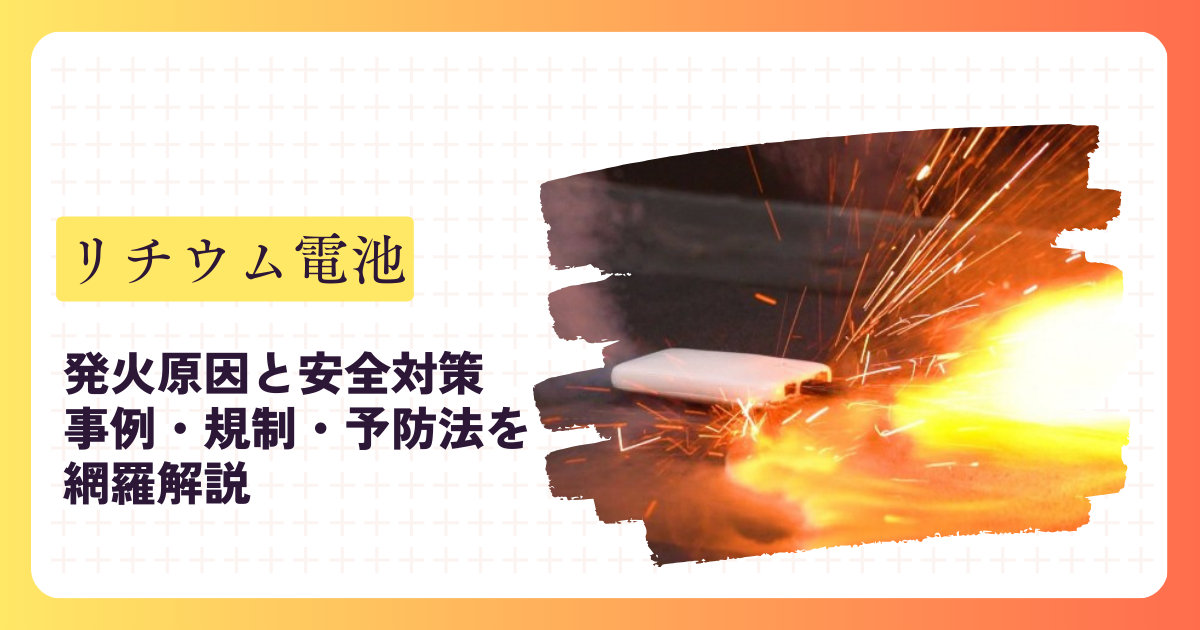
リチウム電池の発火原因と安全対策|事例・規制・予防法を網羅解説
スマートフォンやモバイルバッテリー、電気自動車など、私たちの暮らしに欠かせないリチウム電池。便利で身近な存在ですが、「突然発火した」「充電中に爆発した」といった・・・
アメハチのネットビジネス最初の一歩