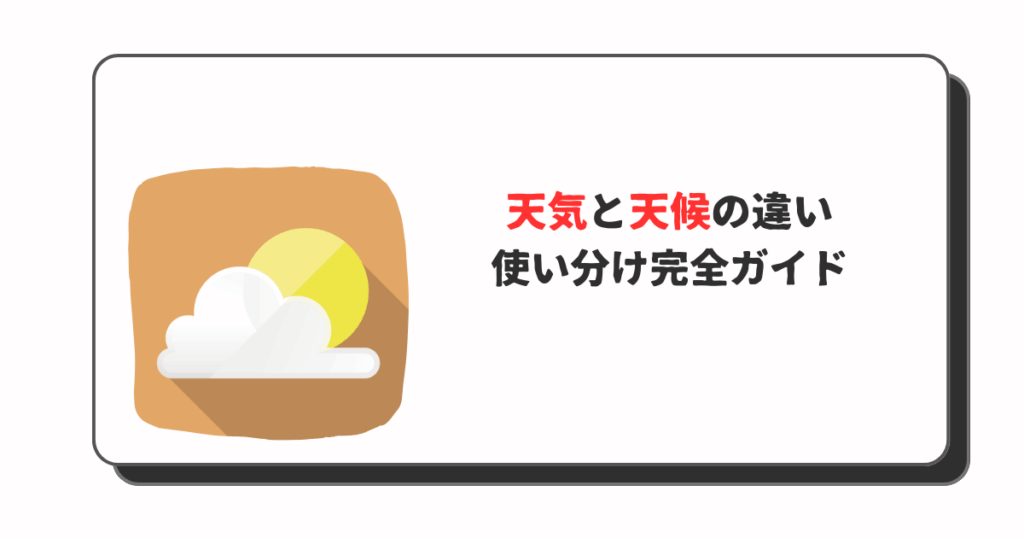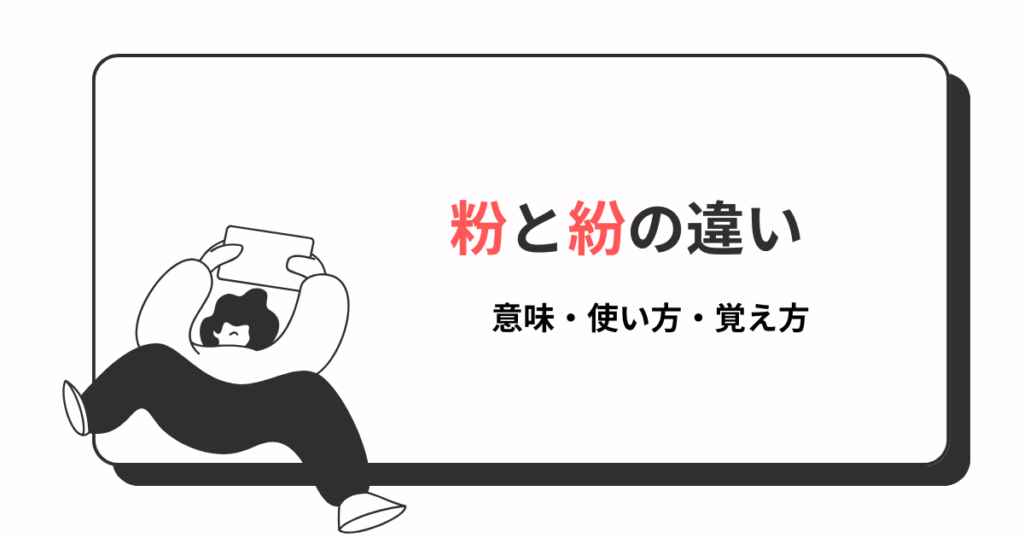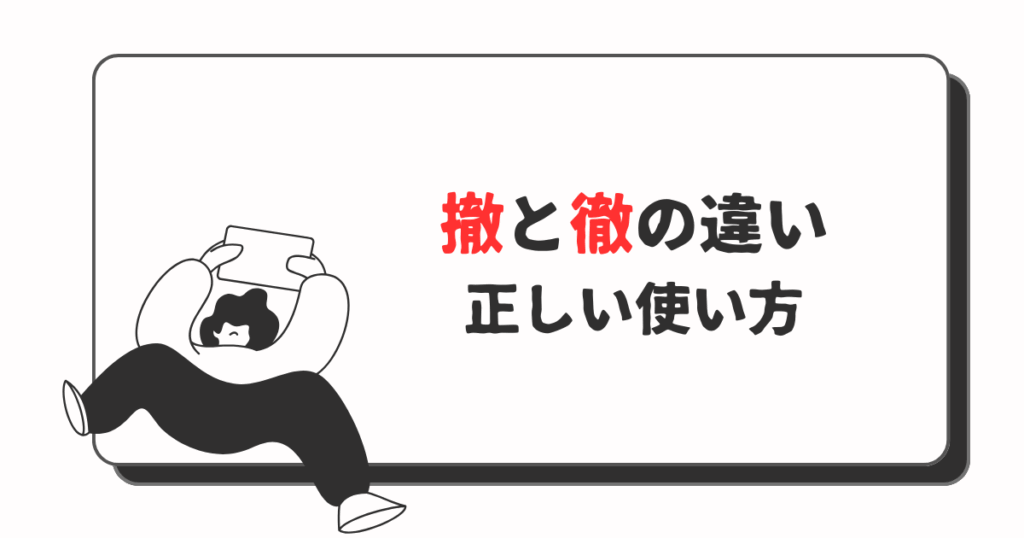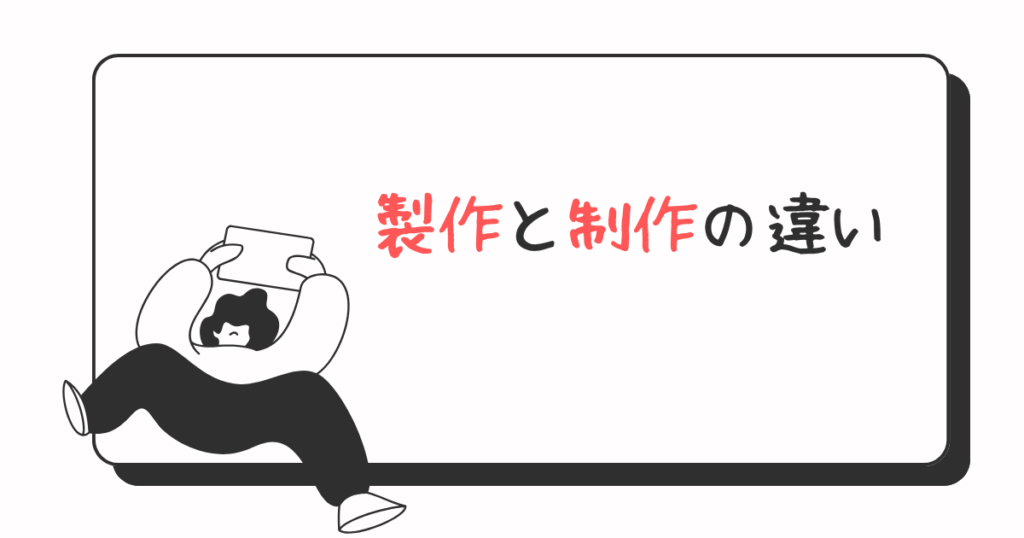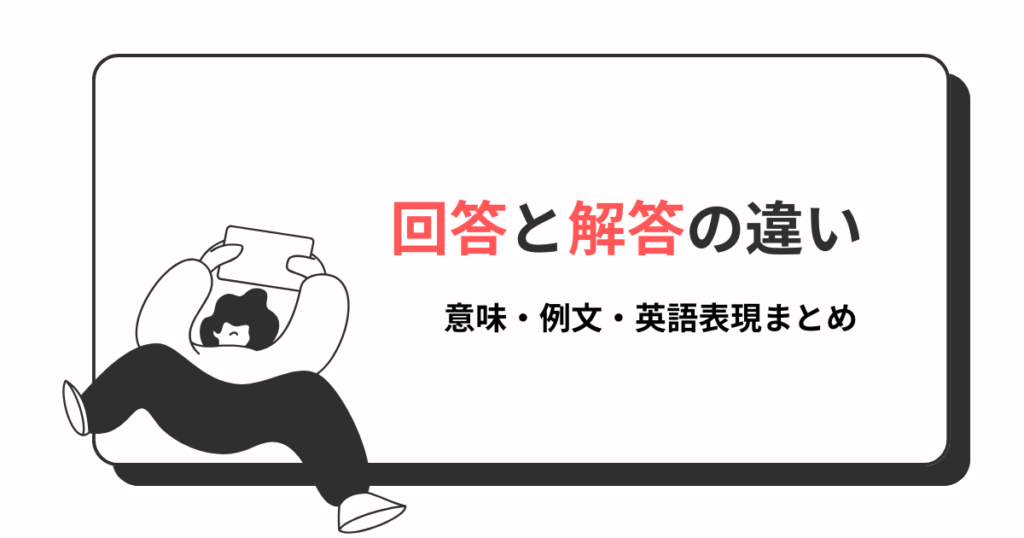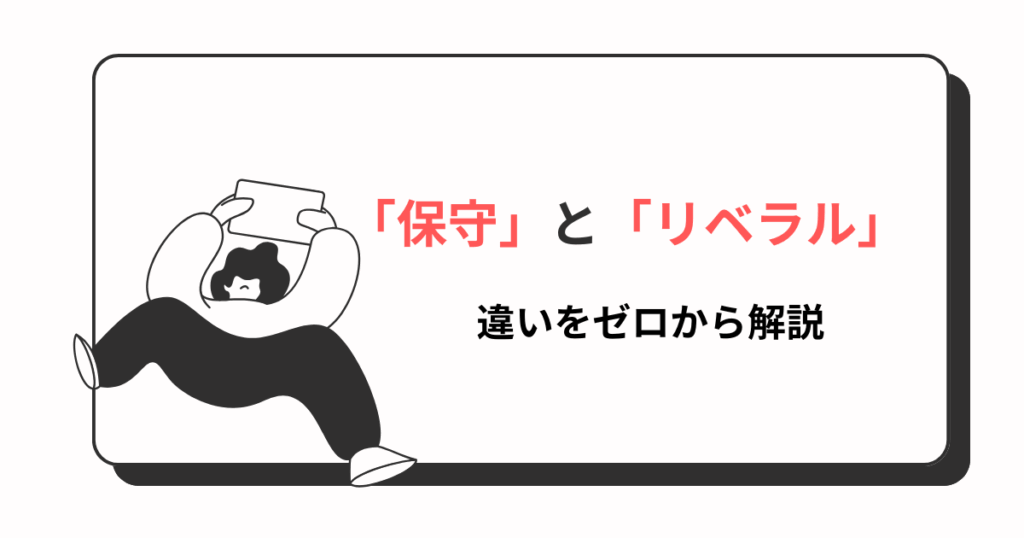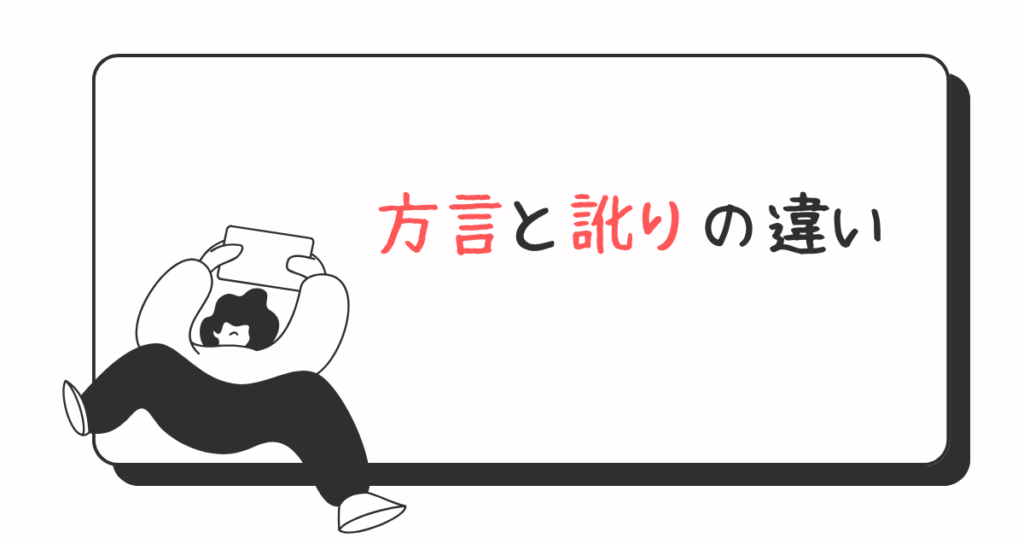
日本には地域ごとの多様な言葉があり、しばしば「方言」と「訛り」という言葉が混同されがちです。これらは似て非なる概念ですが、その明確な違いを理解している方は意外と少ないかもしれません。
この記事では、この二つの言葉が何によって区別されるのか、そして「訛り」が「方言」の要素の一つであるという関係性に注目し、それぞれの言葉が指し示す具体的な範囲を分かりやすく解説していきます。
「方言(ほうげん)」とは?
方言とは、全国で使われる「標準語」とは違って、特定の地域で使われている独自の言葉のことです。地域の話し方や言葉づかいの特徴全体を指していて、次のような要素が含まれます
方言に含まれるもの
- 発音:その地域特有のアクセントやイントネーションがあります。たとえば「訛り(なまり)」も方言の一部です。
- 言い回しや表現:標準語にはない独自の言い方があります。
- 特有の単語(語彙):その地域だけで通じる言葉や言い回しがあります。
方言の特徴と例
- 「関西弁」「京都弁」などのように、方言は「~弁」と呼ばれることが多いです。
- 「方言」という言葉は、「地方のことば」という意味です。
- 方言の大きな特徴は、標準語にはない言葉があることです。
たとえば・・・
- 北海道の「なまら」=「とても、すごく」
- 沖縄の「めんそーれー」=「いらっしゃい」
- 東北地方の「こわい」=「疲れてしんどい」
- 東北地方の「めんこい」=「かわいい」
方言は、特定の地域で広く使われている必要があります。一時的な流行語や個人の造語は方言とは言えません。
地域独自の発音や言葉のせいで、他の地域の人には聞き取りづらい場合があります。特に、標準語を使う地域と交流が少ないほど、その傾向が強くなります。
訛り(なまり)とは?
「訛り(なまり)」とは、その地域ならではの発音の違いのことを指します。標準語とはちょっと違ったアクセントや話し方などで、「方言」の中でも音の特徴に関わる部分です。
訛りに含まれる要素
- アクセント:単語のどこを強調するかの違い
たとえば、「雨(あめ)」という言葉のアクセントは、東京では「あ」に、関西では「め」にあります。
日本語のアクセントは主に「東京式」「京阪式」「無アクセント」の3種類があります。 - イントネーション:文全体の音の高低や、感情の表し方の違い
声のピッチの変化で、意味や印象が変わることがあります。 - 発声法:声の出し方や口の動かし方
たとえば、東北地方でよく知られる「ズーズー弁」は、発声の特徴が訛りとして表れています。
「訛」という漢字の意味
- 「訛」という漢字には「誤り」「いつわり」などの意味があります。
また、「変わる」を意味する「化」という字が含まれていることから、本来の使い方から外れて変化した発音という意味で使われています。 - 英語では「accent(アクセント)」と訳されることが多いです。
まとめ
日本の地域ごとの話し方には、「方言」と「訛り」という二つの言葉があります。それぞれの意味をきちんと理解すると、言葉の奥深さがおもしろく感じられるはずです。
方言とは
- 標準語とは違う、地域特有の言葉づかいのこと
- 発音、言い回し、語彙(使う単語)など、幅広い言語の特徴が含まれます
- 例:「なまら(北海道)」「めんそーれー(沖縄)」「めんこい(東北)」など
訛りとは
- 地域に根付いた発音の違いを指す言葉
- アクセント・イントネーション・発声法などの音声的特徴が中心
- 例:「雨」のアクセントが東京と関西で違う/東北のズーズー弁など
両者の関係性
- 訛りは方言の一部であり、方言の「音」に関する特徴を指します
- 方言は「訛り」に加えて、独自の表現や言葉も含む、より広い概念です