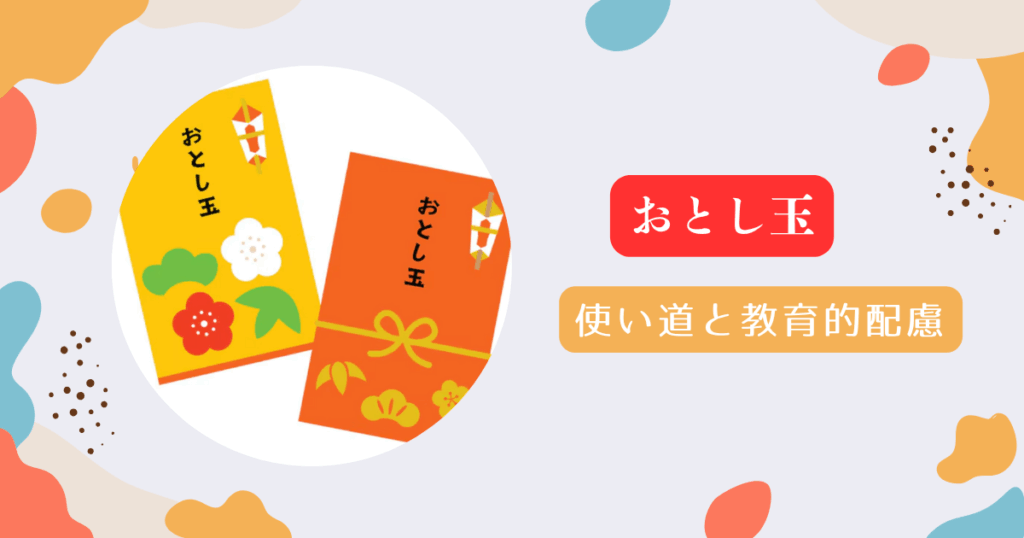「お年玉って自由に使わせていいの?」「貯金させるべき?」
お年玉は子供にとって特別なお金ですが、使い方次第で金銭感覚や価値観の育成につながります。自由に使わせるか、親が管理するか、年齢によっても考え方はさまざまです。
この記事では、お年玉の使い道と教育的配慮について、貯金・買い物・体験などの活用例を年齢別に整理。親の関わり方や声かけの工夫まで、納得感ある判断材料を丁寧に紹介します。
お年玉の使い道はどう決める?
お年玉は、子供にとって「自由に使える特別なお金」としての意味を持ちますが、使い方次第で金銭感覚や価値観の育成につながります。ここでは、使い道の考え方と年齢別の傾向、親の関わり方について整理します。

自由に使わせる?親が管理する?
使い道の決め方は、家庭の方針と子供の年齢によって異なります。未就学児?小学生では、親が管理し「一部を使わせる」「全額貯金する」などの選択が一般的です。
中高生になると、ある程度自由に使わせる家庭も増えますが、「使い道を報告する」「一部を貯金する」などのルールを設けることで、金銭感覚の育成につながります。
年齢別の使い道の傾向とおすすめ例
- 未就学児:絵本・文具・お菓子など、親が選んで使うケースが多い
- 小学生:おもちゃ・ゲーム・本など、本人の希望を聞きつつ一部管理
- 中高生:文具・ファッション・交際費など、自由度が高まりつつも使い方の説明を促す
- 大学生:貯金・趣味・交通費など、自己管理が基本だが「貯める意識」を促すと効果的
貯金・買い物・体験への使い方のバランス
お年玉は「使う・貯める・体験に使う」の3つのバランスが大切です。
たとえば、
- 一部を貯金(将来の目標に向けて)
- 一部を買い物(欲しいものを自分で選ぶ)
- 一部を体験(映画・イベント・習い事など)
というように、使い方を分けることで「お金の価値を実感する機会」になります。親が一緒に考えることで、子供の納得感も高まります。
教育的配慮としての関わり方
お年玉は、単なる「臨時収入」ではなく、子供の金銭感覚や価値観を育てるチャンスでもあります。ここでは、親がどのように関わることで教育的な効果を高められるかを整理します。

金銭感覚を育てるための声かけ
お年玉を渡した後、「何に使いたい?」「どうしてそれを選んだの?」といった声かけをすることで、子供自身が“お金の使い方”を考えるきっかけになります。使い道を否定せず、選択の理由を聞くことで、金銭感覚と自己判断力の育成につながります。
使い道を一緒に考えるメリット
「一部は貯金にして、残りは好きなことに使おうか」「何か体験に使ってみるのもいいね」など、親子で使い道を一緒に考えることで、子供は“お金の価値”を実感できます。
親が一方的に決めるのではなく、選択肢を提示して対話することで、納得感と自立心が育ちます。
高額なお年玉の扱い方と注意点
祖父母などから高額なお年玉をもらった場合は、全額を自由に使わせるのではなく、「一部は貯金」「一部は親が管理」「一部は使ってよい」など、使い方を分ける工夫が必要です。
金額が大きいほど、使い方の教育的配慮が重要になります。親が「これは大切なお金だから、どう使うか一緒に考えよう」と伝えることで、金銭教育の機会になります。
使い道・教育的配慮に関するよくある質問
お年玉の使い方や親の関わり方については、家庭ごとに考え方が異なり、迷いや不安を感じることもあります。ここでは、よくある疑問に対して、納得感ある判断のヒントを紹介します。
- 全部貯金させるのはかわいそう?
- 「せっかくのお年玉なのに、全部貯金では楽しみがないのでは?」と感じる親もいます。実際、貯金だけでは子供が“お金の価値”を実感しづらいことも。おすすめは「一部を自由に使わせる」「一部を貯金する」など、使い方を分ける方法。使う楽しみと貯める意識の両方を育てることができます。
- ゲームやおもちゃに使ってもいい?
- ゲームやおもちゃに使うこと自体は問題ありません。ただし、「本当に欲しいものか?」「長く使えるか?」などを一緒に考えることで、衝動買いを防ぎ、選択力を育てることができます。使った後に「どうだった?」と振り返ることで、次回の使い方にもつながります。
- 親が使い道を決めるのは過干渉?
- 年齢によっては、親が使い道を決めることが必要な場合もあります。特に未就学児?小学生では、金銭管理が難しいため、親が一部管理するのは自然なこと。ただし、「一緒に考える」「選択肢を提示する」など、子供の意思を尊重する関わり方が理想です。過干渉にならないためには、“対話”が鍵になります。