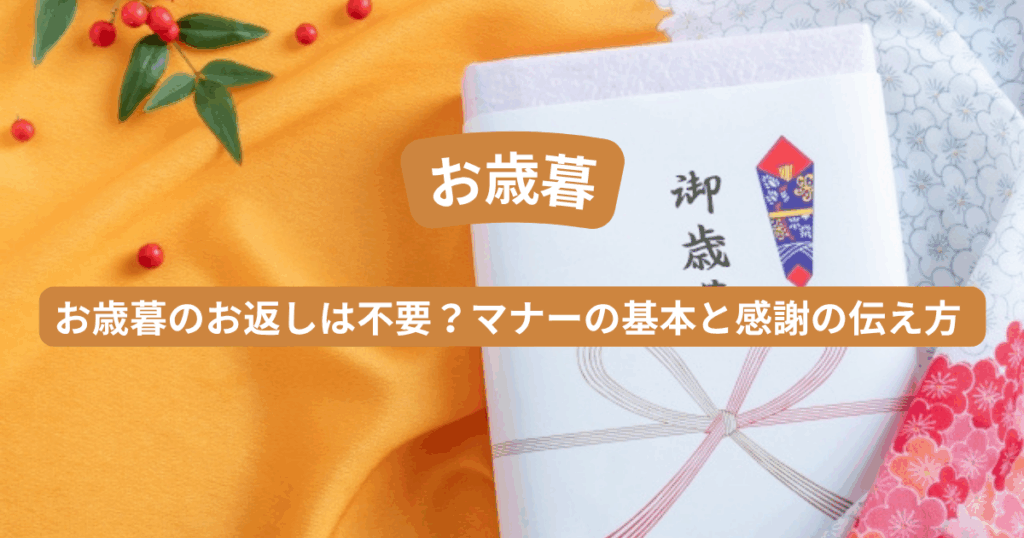お歳暮のお返しに「失礼があったらどうしよう」「何が基本で、どうすれば相手に感謝の気持ちが伝わるのか分からない」といった不安はありませんか?特に、贈答マナーに不慣れな方や、人間関係を大切にしたい方にとっては、頭を悩ませる問題ですよね。
この記事では、お歳暮に関する長年の慣習と現代のマナーをふまえた、お歳暮のお返しに関する「真実」を解説します。
お歳暮へのお返しが基本的に不要である理由から、お礼の気持ちを相手に伝える最適な方法、さらには「お返し」を贈るべき特別な状況と、その際の品物の選び方やマナーまで、本当に知りたい情報が網羅的に手に入ります。読み終える頃には、自信を持ってお歳暮のマナーに対応できるようになるでしょう。
お歳暮に「お返し」はなぜ不要?本来の意味と原則を解説
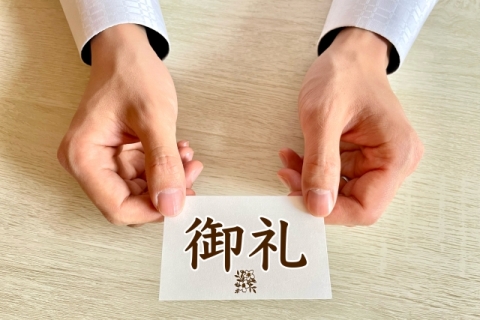
そもそもお歳暮とは、日頃お世話になっている相手へ一年間の感謝の気持ちを贈る季節のご挨拶ギフトです。
基本的にはお返しを前提とした贈り物ではありません。
では、なぜ「お歳暮にお返しは不要」とされているのでしょうか?そして、「お返し」と「お礼」にはどのような違いがあるのでしょうか?
お歳暮がお礼を前提としない贈り物である理由
お歳暮は、お返しを必要としない贈り物であるという原則があります。これは、お歳暮が日本の伝統的な贈答文化において、「日頃お世話になっている相手へ一年間の感謝の気持ちを伝える季節の挨拶」という、特別な意味を持つからです。相手への純粋な感謝と敬意を贈る行為であり、見返りを求める贈り物ではないという考え方が基本にあります。
具体的にご説明しましょう。お歳暮は、まるで「今年も一年間ありがとうございました」と頭を下げるように、ひたすら相手への感謝を品物に込めて贈るものです。そのため、お歳暮をいただいた相手が、すぐさまお返しの品物を贈ることは、贈り主の「感謝の気持ちを伝えたい」という気持ちに対し、かえって負担をかけてしまう場合があるのです。
お返しを贈ることで贈り主が恐縮したり、次のお歳暮を贈る際に相手に「またお返しを選ぶ必要がある」と、心理的な負担を感じさせてしまう可能性も出てきます。これは、相手への配慮というお歳暮本来のマナーから外れることがあります。
このため、お歳暮は相手への感謝を一方的に贈ることで完結する贈り物であり、相互のお返しは必要とされないのが基本です。
「お返し」と「お礼」を混同しないための基本知識
お歳暮を受け取った際、「お返し」と「お礼」の区別がつかず、どうすれば良いか迷う方も多いのではないでしょうか。結論から申し上げますと、お歳暮においては「お返し」は基本的に必要ありませんが、「お礼」は必要不可欠です。
この二つの言葉の意味を正しく理解することが、お歳暮のマナーにおいて非常に重要となります。
「お返し」とは、何かをいただいた場合に、それに対する返礼として同等またはそれに見合った品物を贈る行為を指します。例えば、結婚祝いや出産祝いなどに対する「内祝い」が、まさにお返しの典型例です。
一方、「お礼」とは、相手から受けた行為や気持ちに対する感謝を言葉や行動で伝えることを意味します。品物を贈ることだけがお礼ではありません。
お歳暮は、日頃の感謝を贈るという性質上、相手はお返しを期待していません。にもかかわらず、お返しの品物を贈るということは、相手の感謝の気持ちを「交換条件」のように捉えてしまう場合があり、かえって失礼にあたる可能性も出てきます。
そのため、お歳暮を受け取ったら、まず最優先で感謝の気持ちを伝えるお礼状や電話でお礼をすることに注力しましょう。
お歳暮においては「お返し」は基本不要であり、「お礼」こそが相手への感謝を適切に示すマナーです。
お歳暮へのお礼は「形」より「心」!感謝を伝える正しいマナー

お歳暮はお返しが基本的に不要な贈り物ですが、相手への感謝の気持ちを伝えるお礼は欠かせません。
では、お歳暮に対するお礼は、具体的にどのように伝えるのが正しいマナーなのでしょうか?電話で伝えるべきか、礼状を贈るべきか、あるいはお礼の品物を添える場合はどんなものを選ぶべきか、迷う方も少なくないでしょう。相手に「感謝の気持ち」がしっかりと伝わり、良好な人間関係を維持するためには、形式だけでなく、心を込めたお礼が必要です。
お歳暮を受け取ったらすぐに「お礼」を伝える重要性
お歳暮をいただいた場合、お返しは基本的に不要ですが、感謝の気持ちを相手に伝えるお礼は、できる限り速やかに行うことが非常に重要です。お礼をすぐに伝えることは、相手への敬意と心遣いを示す、大切なマナーだからです。
送った側にしてみれば、自分が贈った贈り物が相手に無事に届いたのか、喜んでもらえたのかどうか、気になっているものです。
「届いたかな?」「気に入ってくれたかな?」といった相手の気持ちに寄り添い、安心させてあげることが大切です。
具体的には、お歳暮が届いてから2~3日以内には、何らかの形でお礼を伝えるのが理想的です。
例えば、親しい相手であれば、まずは電話で一報入れるだけでも十分お礼の気持ちが伝わります。より丁寧なマナーを意識する場合や、目上の方へのお礼であれば、後日改めて礼状を贈ると良いでしょう。
最近では、メールやメッセージアプリでお礼を済ませる場合も増えていますが、あくまで略式であることを理解し、相手との関係性を考慮して選ぶことが必要です。
このように、お歳暮を受け取ったら速やかにお礼を伝えることは、相手への配慮と感謝の気持ちを示す、お歳暮マナーの基本であり、良好な人間関係を維持するための重要な行動です。
相手に合わせた最適なお礼状・メッセージの書き方と例文
お歳暮へのお礼を伝える際、相手との関係性に応じて最適な書き方を選ぶことが、感謝の気持ちをしっかりと相手に届けるために非常に重要です。
例えば、目上の方やビジネス上の相手には、丁寧な礼状(手紙)が最も正式なマナーとされています。時候の挨拶から始まり、お歳暮をいただいたお礼、商品や品物への感想、相手の健康や繁栄を願う言葉、そして日付と署名で構成するのが基本です。
具体的には、
「拝啓 師走の候、〇〇様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、この度は結構なお歳暮をお贈りいただき、誠にありがとうございます。家族一同大変喜んでいただいております。
末筆ではございますが、〇〇様の更なるご活躍を心よりお祈り申し上げます。敬具」
といった形です。
一方、親しい友人や家族の場合は、電話やメール、メッセージアプリでのお礼でも十分気持ちが伝わります。この場合は、受け取ってすぐに連絡すること、そして「ありがとう」「とても美味しかった」といった素直な感想を伝えることが大切です。
しかし、略式だからといって雑にならないよう、丁寧語を使い、絵文字の多用は控えるなど、最低限のマナーは守りましょう。
どんな方法であれ、共通して避けるべきは、お返しに関する言及や、受け取った品物への不満です。また、お礼が遅れてしまった場合は、遅れたことへのお詫びを一言添えるのがマナーです。
お礼状に添える品は「お返し」ではない、その目的と選び方
お歳暮をいただいた際、お礼状や電話での感謝だけでなく、さらに丁寧な気持ちを伝えたい場合に、品物を添えることを考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、ここで大切なのは、この添える品物がお歳暮の「お返し」ではない、という点です。あくまで「お礼の気持ちを補完する贈り物」という位置づけであることを理解しましょう。
これは、お歳暮がお返しを必要としない贈り物であるという基本原則を守りつつ、相手への感謝を最大限に伝えたいという気持ちから選ばれる行動だからです。
あくまで、あなたの感謝の気持ちを形にしたギフトとして、相手に気兼ねなく受け取ってもらうためのものです。
品物を選ぶ際には、相手に気を遣わせない配慮が必要です。例えば、いただいたお歳暮の半額以下程度の商品がおすすめです。
具体的には、日持ちのするお菓子や相手の家族構成を考えた消耗品などが人気です。例えば、せんべいや焼き菓子、普段使いできるタオルなどが挙げられます。
熨斗(のし)をかける場合は、「御礼」と表書きし、紅白蝶結びの水引を使います。時期としては、お歳暮をいただいた後、できるだけ早い時期にお礼状に添えて贈るのがマナーです。
このように、お礼状に添える品物は、お歳暮への「お返し」ではなく、「より深い感謝の気持ち」を伝えるためのものです。相手に負担をかけない品物選びを心がけることで、あなたの感謝の気持ちがより伝わり、良好な関係を保つことができるでしょう。
「お歳暮のお返し」を検討すべき特別なケースと贈る際のマナー
お歳暮に対するお返しが基本的に不要であるという原則を踏まえた上で、例外的にお返しを贈ることを検討すべき特別なケースと、その際の具体的なマナーについて解説します。
お歳暮は感謝を伝える贈り物ですが、状況によってはお返しを贈ることで、より丁寧に相手への感謝の気持ちを示す場合があります。
しかし、「どのような場合にお返しを贈るのが適切なのか?」「贈るなら、どのような品物を選ぶべきか?」「熨斗(のし)や時期のマナーは?」といった疑問が生じるでしょう。これは、マナーを重んじる方や、相手との関係性を大切にしたい方が特に知りたいポイントです。お返しが必要ではない場合に無理に贈ると、かえって相手に気を遣わせてしまう可能性もあるため、贈るかどうかの判断は慎重さが必要です。
お歳暮に「お返し」を贈ることを検討するべき特殊な状況
お歳暮は基本的にお返しが不要な贈り物ですが、一部にはお返しを贈ることを検討すべき特別なケースも存在します。これは、お歳暮が持つ「日頃の感謝」という意味合いを超え、相手との関係性や特定の慣例が影響する場合です。
お返しが必要となる場合の多くは、ビジネス上の慣例や、相手との個人的な関係が非常に密接である場合に見られます。
例えば、取引先との円滑な関係維持のため、あるいは特定の業界内で慣習となっている場合です。
また、お歳暮という形をとりながらも、実際には祝い事(出産祝いなど)の返礼や、お世話になったお礼の品物として贈られていると判断できる場合もこれに該当します。相手が強くお返しを期待しているような言動が見られる場合も、感謝の気持ちを贈るというマナーから、お返しを検討する必要が出てくるでしょう。
具体的な判断基準としては、まず相手との関係性を深く考慮してください。個人的なお礼や祝い事が背景にあるか、ビジネスマナーとしてお返しが一般的かなどです。
次に、贈られたお歳暮の商品が、一般的なお歳暮の品物の相場を大きく超える場合や、普段から互いに贈り物を贈る習慣がある場合も、お返しを検討するきっかけとなります。しかし、相手に「お返しを必要としない」という気持ちが明確にある場合は、無理に贈るとかえって失礼にあたる可能性があることも忘れないでください。
感謝の気持ちが伝わる「お返し」の品選びのポイントと注意点
お歳暮は基本的にお返しが不要な季節の贈り物ですが、特別な場合にはお返しの品物を贈ることもあります。そうした際に相手に心から喜んでいただけるよう、感謝の気持ちが伝わるギフト選びのポイントと注意点を解説します。
お返しの品物選びで最も大切なのは、相手への感謝の気持ちを形にすることです。まず、お歳暮をくださった相手の好みやライフスタイルを考慮しましょう。例えば、家族構成や年齢、趣味嗜好(しこう)などを踏まえて選ぶと、相手への気遣いが伝わり、より感謝の気持ちが深く伝わります。
食品を選ぶなら、日持ちするものや、相手が消費しやすい個包装の商品が人気です。また、アレルギーや好き嫌いにも配慮し、誰もが楽しめるものを選ぶのがおすすめです。
次に、お返しの品物の相場は、いただいたお歳暮の3分の1から半額程度が基本とされています。高価すぎるお返しは、かえって相手に気を遣わせてしまう可能性があるため、避けるのが賢明です。例えば、3,000円程度のお歳暮であれば、1,000円から1,500円程度の商品を目安に選ぶとよいでしょう。予算内で質の良い品物を選ぶことが、相手への配慮につながります。
注意点としては、「内祝い」(出産や結婚などのお祝いへのお返し)と同じような品物を選ばないことです。お歳暮に対するお返しは、内祝いとは異なる意味合いを持つため、お祝いごとのギフトでよく選ばれる品は避けるのが基本です。
また、お歳暮を受け取ってすぐにお返しを贈るのではなく、お歳暮が届いたことを確認し、まずはお礼の連絡(お礼状や電話)をするのがマナーです。お返しを贈る場合も、お歳暮が届いてから1週間以内を目安に贈るのが適切です。遅くなりすぎると、相手に心配をかけてしまうこともあります。
お返しを贈る時期、熨斗(のし)の表書きと水引の正しい選び方

お歳暮はお礼の気持ちを贈る贈り物のため、お返しは基本的に必要ありません。しかし、特別な場合にはお返しを贈ることを検討することがあります。その際、相手に失礼なく感謝の気持ちを伝えるためには、贈る時期や熨斗(のし)のマナーを正しく理解することが極めて重要です。
お返しの品物には、必ず熨斗を付けるのがマナーです。水引は「紅白蝶結び」を選びましょう。蝶結びは「何度でも結び直せる」という意味合いがあるため、繰り返しても良いお祝い事や季節の挨拶に用いられます。お歳暮が「日頃の感謝」を表す贈り物であるため、この水引が適しています。表書きには、水引の上に「御礼(おれい)」と書くのが一般的です。相手によっては、「お歳暮」と書く場合もありますが、「御礼」の方がより感謝の気持ちが伝わり、丁寧な印象を与えます。水引の下には、贈り主の氏名をフルネームで記載ください。
これらのマナーをきちんと守ることで、お返しが相手への真心を込めた贈り物となり、良好な人間関係を築くことに繋がります。形式的な部分ですが、相手への配慮を示す重要な要素ですので、抜かりなく準備を進めることが大切です。
まとめ
この記事では、お歳暮をいただいた場合に、お返しが必要かどうか、そしてお返しを贈る場合のマナーについて詳しく解説しました。お歳暮は日頃の感謝を伝える贈り物であり、基本的にお返しは必要ないとされていますが、状況によってはお返しを検討する場合もあります。
お歳暮のお返しについてのポイントは以下の通りです。
- お歳暮は基本的にお返しが必要ない贈り物です
- お歳暮が届いたら、まずはお礼状や電話で感謝の気持ちを伝えましょう
- もしお返しを贈る場合は、いただいた品物の3分の1から半額程度が相場です
- お返しの品物は、相手の好みやライフスタイルを考えて選びましょう
- 熨斗(のし)は紅白蝶結びを選び、表書きは「御礼」とするのが基本マナーです
- お返しを贈る時期は、お歳暮が届いてから1週間以内を目安にしましょう
お歳暮に関するマナーは、相手への感謝と配慮の気持ちを伝えるために存在します。必要以上に気を遣いすぎず、基本的なマナーを押さえることで、相手との良好な関係を保ちながら、スムーズな贈り物のやり取りができるでしょう。この記事が、皆さんのお歳暮に関する疑問や不安を解消し、自信を持って対応する一助となれば幸いです。